こちらの記事は2024年8月19日に更新されました
- 子どもが不登校になっているのは、親の関わりが原因ではないか?
- 親としての行動や関わり方を見直して子どもの不登校を解決したい。
GoTodayでは、日々さまざまな不登校のご相談を受けており、復学までの支援をしています。
その経験から、お子さんが不登校になってしまうご家庭の親御さんには、決定的な特徴が見受けられます。
お子さんが不登校になりやすい親御さんの特徴と解決策をお伝えしますので、最後までお読みください。
小中学生復学支援GoTodayでは、不登校克服を専門に、小中学生のお子さんの不登校でお悩みのご家庭に「親が変われば、子は変わる」という考えに基づいた支援を提供しています。
2018年から活動を開始し、毎年約40名のお子さんが当支援を通じて復学しています。GoTodayでは、遅刻や早退をせずに毎日教室に通えるようになるまで、復学期間を約3〜4ヶ月以内で教室への復帰を行えるように支援を行っています。
復学後も継続的に登校できるよう、ご家庭に合ったサポートを続けています。
GoTodayについての詳細は、こちらをご確認ください。
最終更新日:2024年8月16日
不登校になる親の決定的な特徴について
不登校になりやすいお子さんを持つ親御さんは、過保護で心配症、お子さんに対して過干渉になりがちです。
このような親御さんは、お子さんが自分で何かをする前に手を差し伸べ、何とかして苦労せずに助けたいと一生懸命になります。その結果、逆に子どもの自立を妨げてしまうことがあります。
これは、子どもを思う気持ちが強いからこそ起こることで、親御さんとしては何とかして子どもを助けたい、支えたいという強い愛情からの行動です。しかし、時にはその優しさが子どもの自立を阻んでしまうことがあるということを考えなければいけません。
親は自分の子どもが苦しんでいる姿を見たくありませんし、失敗や挫折から守ってあげたいと思うのは当然のことです。
特に、繊細で感受性が強いお子さんを持つ親御さんは、子どもの不安や心配を軽減するために、先回りして助けようとする傾向があります。
しかし、その結果として、お子さんが自分で考えたり、行動したりする力を育む機会を失い、親御さんがいないと不安を感じるようになってしまうことがあります。これは親御さんにとって大きな葛藤があると思いますがで、決して親御さんの行動が「悪い」というわけではありません。
過保護・過干渉は依存する子を作る
たとえば、朝の忙しい時間に「早く起きなさい」「忘れ物はない?」と声をかけるのは、親御さんが子どもの一日を心配しているからこそです。
また、学校から帰ってきた後も、親御さんが「塾の時間だよ」「宿題やったの?」と声をかけるのは、子どもの将来を思ってのことです。
これらは、親御さんが自分の経験から得た知恵や学びを、子どもに伝えたいという優しさからくるものです。しかし、こうした声かけが、お子さんにとっては「親が全部やってくれるから、自分で考えなくても大丈夫」という依存心を生み出すことがあります。
このように、親御さんが心配して先回りすることで、子どもは自分で物事を決める力を持てず、このような環境に慣れてしまうと、学校という環境での自立が難しくなります。
家庭では親が支えてくれるけれど、学校では同じようにしてくれる人がいない。そう感じた子どもは、次第に学校に行くことが負担になり、不登校につながることがあるのです。
不登校の原因についてはこちらで解説していますので参考になさってください。
また、親御さんがお子さんを一番に考えるあまり、子どもが家族の中心になりがちです。その結果、子どもは家庭と学校の環境の違いに戸惑い、学校生活でのストレスが増してしまうこともあります。
まとめると、親御さんがお子さんを思う気持ちは、決して間違いではありません。むしろ、その優しさや愛情は、お子さんの成長にとって大切なものです。
しかし、少しずつお子さんに自分で考える時間を与え、自立を促すことも重要です。
親御さんもお子さんと一緒に少しずつ成長し、共に歩んでいくことが、不登校を克服するための一歩となります。
不登校を解決するには親が変わることが鍵
不登校を解決するには、まず「親が変わること」が鍵となります。
不登校になりやすいお子さんは、繊細で感受性が非常に強く、他の子どもとは異なる感じ方をします。
例えば、クラスメイトが怒られている様子を見て、自分が怒られているかのように感じたり、友達の悪口を聞いて自分まで気分が沈んでしまうことがあります。
こうしたお子さんは、事実を誇張して受け取ったり、将来のことを過剰に心配したり、人の気持ちを読みすぎて疲れることが多いです。
このような性格を持つお子さんには、一般的な子育て(例:褒めて育てる等)ではうまくいかないことが多いです。
そこで、親がまずお子さんの性格に合わせた対応に変えていくことが重要です。
特に思春期に差し掛かると、ますます周囲の言動に敏感になり、親の対応次第では強く反発することもあります。だからこそ、親が子どもの性格に合わせて、柔軟に対応することで、お子さんんが自分で考え、自立していけるように導くことができます。
不登校になりやすいお子さんの性格について、さらに詳しく知りたい方は、こちらをお読みください。
【対策】親はどのように変われば良いか
多くの親御さんは、子どもが不登校になった時、「自分がもっと愛情を注げば、子どもは元気になる」と考えがちです。もしくは、そのようにアドバイスをされることが多いと思います。
寄り添い、無理をさせず、子どもの望む環境を整えることが大切だと考えるのは良いことですが、メリハリがなく、わがまままで認めてしまうと、子どもの居心地が良くなりすぎて、自立心や協調性が育たず、学校に戻ることが難しくなってしまうことがあります。
子どもを守りたいという親の気持ちは当然ですが、過保護になりすぎると、かえって子どもの成長を妨げてしまうのです。
例えば、「来れる時に来れば良い」と先生から言われたり、発達障害を疑い、診察を勧められるケースもあります。
しかし、不登校は発達障害が原因であるとは限りませんし、診断がついてしまうことで、かえって親もお子さんも混乱することがあります。
お子さんが自立し、学校生活に戻るためには、親が「子どもを変えよう」とするのではなく、「自分自身を変える」ことが必要です。
考え方を変え、その考え方に基づいた行動をとることで、子どもは間接的に自然と変わっていきます。
親が安心して、自信を持って対応できるようになると、お子さんもその姿を見て成長し、不登校を乗り越えることができます。
親の対応を見直し、復学した事例
GoTodayの復学支援を受けて復学した事例をいくつかお伝えしたいと思います。
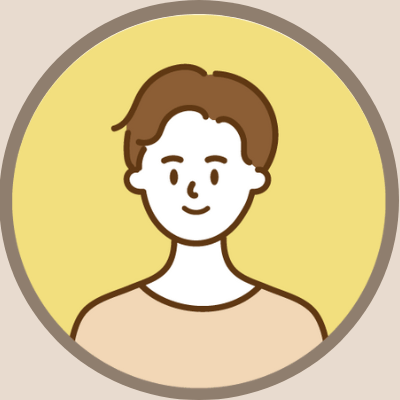
不登校1年半以上・昼夜逆転「先回りせず見守ることが自立につながると実感しました」
《体験談全文はこちら》
復学支援を受ける前の状況
- 不登校になってからは基本的に昼夜逆転の生活
- 暴力や暴言はありませんが、ストレスが溜まってくると小2の弟に当たり散らし泣かせます。
- 先生にも学校にも友達にも問題は無く…本当に本人も分からないようで、ただただ朝になると行きたくない。でも学校にはまた行きたい。原因が分からず対処のしようもなく困り果てていました。
復学支援を受けて変わった様子
- ご指導を受け、子供への私の対応を変えて行ったところ、長男次男ともみるみる自立していったように思います。
- ご指導が無ければ私が先回りしてどうにかしていた場面で、ご指導のお陰で口出しせず見守っていた所、きちんと自分で対処出来た時には感動さえ覚えました。
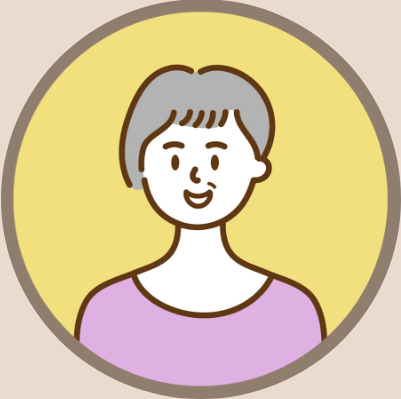
3年4ヶ月不登校・音や匂いに敏感になり、食事も喉を通らなくなっていました。
《体験談全文はこちら》
復学支援を受ける前の状況
- 小学5年生になり子供が給食が食べれないと言い、子供の心身の不調がだんだんひどくなっていき、学校に行きにくくなりました。
- 音や匂い等色々な物に敏感になり、家での食事量も減り、食事が全く喉を通らなくなり、学校に行けなくなりました。外にも出たがりません。
- 病院に半ば無理やり連れていき、情緒面でかなり幼いと言われました。
復学支援を受けて変わった様子
- 子供が動き出すのを待ってみると、自分なりのペースで自分で考えて動くようになりました。
- ご指導で背中を押してもらった子供は、毎日学校に行き、高校受験を終えて、電車通学をして学校に通っています。
- 私は、人の目を気にしたり、周りから言われたりして、それを子供に対応してしまう事がありました。
- 子供によかれと思ってやっていた事や周りが言うからとやっていた事が子供にとって辛い事だったんだなと改めて思いました。

約5ヶ月不登校「子供が考え、行動し始めることを待てるようになりました」
《体験談全文はこちら》
復学支援を受ける前の状況
- 学校に行っている時とあまり変わりはありませんでしたが、学校や勉強については話したくないと言っていました。
- 担任の先生から何度かお電話をいただいていましたが、最初2回ほ どは出ていましたが、その後は拒否していました。
復学支援を受けて変わった様子
- 復学支援を受けて朝の起床から、宿題、お風呂、テスト勉強(テスト勉強の予定を私が手 を出して作成していました)、就寝まで、するしない、またはいつするのかは子供の問題だと教えていただき、口出し手出しをやめました。
- 子供が考え、行動し始めることを待てるようになりました。そうすると子供も自ら行動するようになりました。
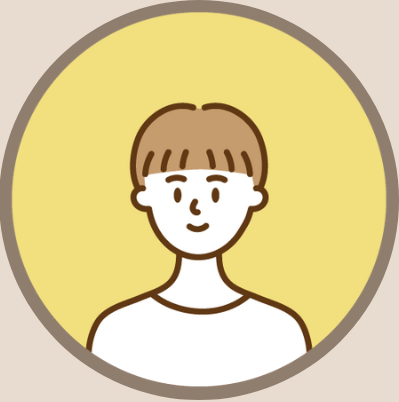
小5長女・小3長男の不登校 「子ども達の様子を細かく相談し、一つ一つ的確なアドバイスをいただきました」
《体験談全文はこちら》
復学支援を受ける前の状況
- お友達と遊ぶことが大好きだったのですが最近はうまく付き合えないのか、友達と遊ぶことがなくなりいつも家でテレビを見ています。
- 姉は最初はやる気もあって塾に楽しく通っていたもののだんだんしんどくなってきて、塾の宿題や学校の宿題を完璧にやらなくてはと背負い込み、息抜きの方法も分からず4年の2月(塾の学年が上がるタイミング)で塾に行きたくない、学校も行きたくないと休むようになりました。
復学支援を受けて変わった様子
- 反抗してイライラしてすぐにきょうだいに八つ当たりの暴力をしていた長女が嘘のように穏やかになりました。
- 過干渉で口うるさかった私は復学支援のおかげで人格が変わって見えるほど黙って見守ることができるようになったのです。
- 「毎日楽しいんだぁ!」と生き生きと楽しんで学校に行くようになりました。
- そして大変だった今までは一体何だったのかと思うほど子育ては楽になりました。
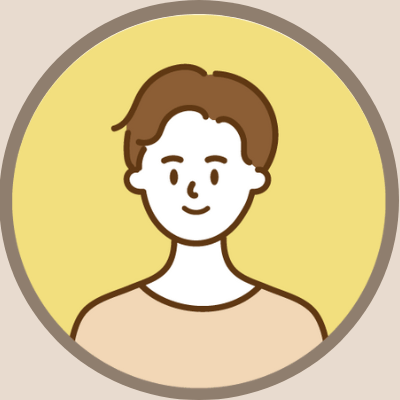
朝起きると「体調が悪い」と言い、昼夜逆転し、自分の髪の毛を抜いていました。
《体験談全文はこちら》
復学支援を受ける前の状況
- 友達がいない不安からだと思っていましたので、「みんな新しいクラスで友達を作ろうと思っている。行けば友達ができるから。」と、泣いて嫌がる娘を無理矢理制服に着替えさせ、学校まで車で送っていました。
- しかし、1学期の期末テストの翌日から学校を休み、夏休み明けも教室へ行くことはできず、不登校になりました。
- 昼夜逆転をし、夜中はスマホやパソコンでゲームをしたり、動画を見ていました。
- 自分の髪の毛を抜いていて、部屋に髪の毛がたくさん落ちているのも気になっていました。
復学支援を受けて変わった様子
- 口を出してしまう方が楽なこともありますが、その気持ちをおさえて、口を出さずに待つことができるようになりました。
- 失敗を私のせいにすることもありましたが、娘が自分で考えて動くようになってからは、このようなことを言わなくなりました。
GoTodayの復学支援
GoTodayでは、「親が変われば、子は変わる」という考えを基本に親御さんか変わることで、間接的にお子さんが変わり、学校に復帰できるように支援を行っています。
不登校になりやすいお子さんの性格を見極めながら、親御さんはどのように対応したら良いのかを毎日の電話と親子の会話ノートを通じて指導していますので、親御さんも迷いなく対応していただけます。
親御さんだけでの対応が難しい場合は、お気軽にご相談ください。
GoTodayの復学支援の内容については下記のページをご確認ください。
また、お悩み別の考え方・対策についても書いていますのでお子さんの状況に合ったページをご確認ください。
まとめ
不登校になりやすい親の特徴
- 過保護・過干渉:子どもが自分でやる前に、親が先回りして手を差し伸べてしまう。
- 心配症:子どもが失敗しないように、過剰に心配してサポートしようとする。
- 子どもが家族中心:家では親が全てサポートしてくれるが、学校ではそうでないため、学校に行くのがつらくなる。
不登校を解決するには親が変わることが鍵
- 子どもの繊細さを理解する:繊細で感受性が強い子どもは、他の子よりも周囲の影響を受けやすい。
- 柔軟な対応を心がける:親が子どもの性格に合わせて、対応を変えることが大切。
- 通常の育て方が通じないことも:褒めて育てるなどの一般的な方法が、逆効果になることもある。
親が変わるための対策
- 愛情だけでは解決できない: 愛情や過保護だけでは、かえって子どもの成長を妨げることがある。
- 発達障害と決めつけない: 不登校が発達障害とは限らないので、安易に診断を受けるのは慎重にする。
- 親自身の行動を変える: 子どもを変えるのではなく、親がまず自分の考え方や行動を変えることが必要。
- 親が安心することが大事: 親が安心して対応できれば、それが子どもにも良い影響を与え、成長につながる。
こちらのブログでお伝えしていることは、基本的な考え方になりますので、ご家庭によって対応が変わる場合があります。独断で対応されないことをお勧めします。

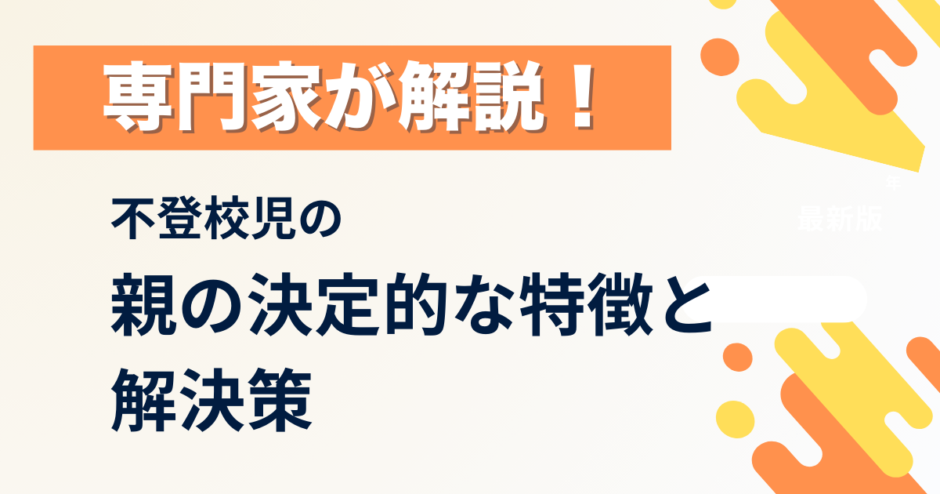
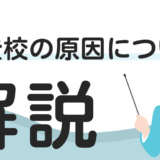
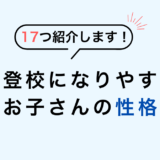
そもそも母親だけのせいにしている時点で古い考えだと思います。ご主人も仕事に出る時間なのに気にも止めずって。
今共働きの家庭がほとんどなのに専業主婦が前提なのがすごい。
S.T様
初めまして。
ご貴重なコメントいただき、ありがとうございます。
S.T様は「専業主婦が前提なのが」と書いてくださっていますが、実際に、復学支援を受けられる9割以上のご家庭が共働きのご家庭ですので、専業主婦を前提に書いてはおりません。
「母親」が変わる。と、強調していますので「母親」だけが悪いと捉えられても仕方がないかと思います。
ただ、お伝えしたいことは「母親」が悪いということをお伝えしたいのではなく、「母親」は子どもにとって一番身近な存在であり、一番影響を受ける存在であるということです。
お子さんは親の言動をよく見ています。
特に不登校になるお子さんは感受性が強いお子さんですから、母親の言動や考えはお子さんに影響を与えます。
もちろん、私たちは父親に対しても対応を変えていただくように指導させていただいております。
一概には言えないと思いますが、確かに子供のうちは父親より母親の影響を受けやすいのは確かだと思います。接する時間も長いのが母親です。
だから、母親を強調したのだと捉えてます。良くも悪くも母親の影響を受けやすいと言うことです。
私の子供は今年から高校一年生ですが中学の頃不登校ということもあり通信の高校にしました。これから不安ですが…
私の妻は、高校の頃不登校になり、通信で高校の資格を取ったようです。私は、どちらかと言うと真逆で皆勤賞に近い感じで普通に学校に行くことが当たり前でした。大学もでてます。子供を見てると、現状が不登校でしたから、母親の影響は大きかったのかなと思ってます。その価値観で子供に接することでその方向に向いてしまったのだと思ってます。親が培ってきた生活が子供に影響が出ますよね。
無理に私の価値観生活にすることではなく今と向き合いながらいい方向に導いてあげればいいと思ってます。
>>ご主人も仕事に出る時間なのに、ご主人のことは気にも止めず。
まずここに違和感を覚えます。朝が忙しいのは父親も母親も同じです。協力してやっていけばいいと言う考えがあれば、このような発言にはならないのではないでしょうか。
そしてやはり母親1人が悪いというお考えが文章から伝わってきます。母親だけに完璧を求めるのは、母親が1番子供の身近にいるという理由だけでしょうか?
不登校の原因は家庭にもあるのは否定しませんが、また家庭だけにあるとも言い切れません。
理不尽ないじめにあったり、教師の言動に疑問を感じて学校に行けなくなる子供もいます。恐らくいじめる側にも家庭内の問題があるのでしょう。
そう考えると、不登校の原因はやはり「家庭」なのかもしれませんね。
yw様
コメントいただき、
ありがとうございます。
「母親1人が悪いというお考えが文章から伝わってきます」
とのご意見ですが、
そのように感じられたということですね。
「母親だけに完璧を求めるのは、母親が1番子供の身近にいるという理由だけでしょうか?」
とのご意見ですが、私どもの復学支援は、ご夫婦で協力していただくことを必須にしております。
面談でもできる限りご夫婦でお越しいただくようにお願いしています。
また母親だけに完璧を求めると書かれていますが、
完璧な子育てを求めているとは書いておりません。
それぞれのご家庭に合った形で、
子育てをしていただけたら良いと
思っております。
子供上位が子供にとって良くないということですよね。私も旦那より子供優先で育ててきました。何でも先回りして、子供が失敗しないように、完璧に連絡帳をチェックして朝の忘れ物チェックを手伝うなど過干渉であることを分かりつつ心配の方が先に立ってしまい我慢できずに、何もかもに手を出していました。よく言うことを聞き、よくしつけられた良い子供で典型的な親にとって都合の良い子です。不登校はありませんが、小学校では自主性がなく、言われないと何も出来ない子供です。
親自身が変わらないと、私は理解できます。
ADHD、ASDのある子ですが、難しいです。声がけには 気をつけてます。例えば、
宿題何時にする予定なのか?命令口調は、言わないよう気をつけてるつもりです。でも、テスト期間近くになると、心配で心配でたまりません。勉強しないのですから。提出物も守りませんし。発達障害がある場合、ある程度過保護になってしまうのではないのか?
ゆき様
コメントいただき、
ありがとうございます。
診断を受けていないお子さんでも、忘れ物や宿題をしないお子さんはたくさんいますし、診断を受けている・受けていないに関わらず、過保護になってしまう親御さんは、過保護になります。
10代の頃、不登校で摂食障害でした
私の母の特徴同じでびっくりしました!
「もう朝よ!起きて!」から始まり、
「何で朝の準備を夜にしておかないの!」
「今日も遅いよ!」
「早く朝ごはん食べて!歯磨きして!」と
立て続けに言ってくる人でした
わたしも、ハイハイ、と無表情でやり過ごし、コミュニケーションはありませんでした。
(母はコミュニケーション取ってるつもりだとおもいますが)
不登校の母って過干渉だし、父親は無関心ですよね。
やはり、子育ては父より母の影響が大きいと思います。いくら父が子育てに参加しても母がダメだと子育てに影響する、、
今、妊娠中ですので、この記事を参考にして子育てしたいと思います
ありがとうございます
まやこ様
コメントいただき、
ありがとうございます。
こちらの記事を参考に参考にしていただけるとのこと、
これから子育て頑張ってください。
大変な時期だと思いますが、
ご自愛くださいませ。
我が子ではありませんが、知っている方のケースがまさに書いてある通りで驚きました。
読んでいて腑におちました。
周りに原因を探す方が多いように思いますが、原因は内にあると思っていました。
[…] 不登校になる子の親の特徴 【危険な落とし穴】不登校中の保健室登校や別室登校 学校に通い、集団生活を送ることが大切な理由 不登校の子どもに対する間違った考 […]