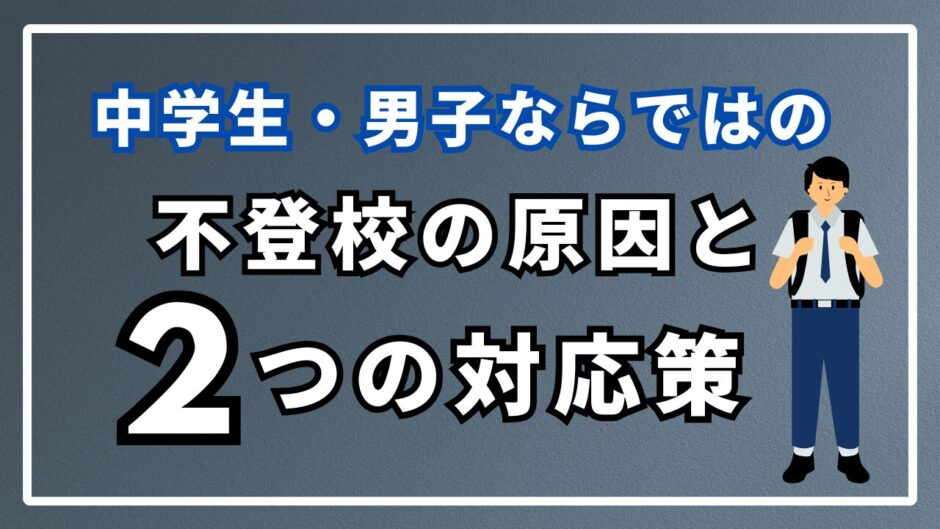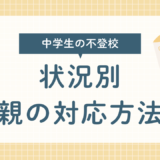- 中学生男子の不登校の原因を知りたい
- 「反抗的な態度」「ゲーム・スマホ依存」などの問題行動にどう対処したら良いかわからない
中学生男子は、反抗的な態度をしたり、時には部屋にこもって静かになったり、何を考えているのか分からない行動をとることがよくありますよね。
例えば、何気なく声をかけた言葉に急に怒り出したり、逆に何も言わずに閉じこもることもあります。
これにどう対応して良いか悩む親御さんも多いのではないでしょうか。
Go Todayでは、300名以上のお子さんの復学していますが、支援してきたお子さんの学年・性別は中学生男子の割合が一番多いです。
この記事では、中学生男子ならではの不登校になる原因と、具体的な対応策を紹介します。
小中学生復学支援GoTodayでは、不登校克服を専門に、小中学生のお子さんの不登校でお悩みのご家庭に「親が変われば、子は変わる」という考えに基づいた支援を提供しています。
2018年から活動を開始し、毎年約40名のお子さんが当支援を通じて復学しています。GoTodayでは、遅刻や早退をせずに毎日教室に通えるようになるまで、復学期間を約3〜4ヶ月以内で教室への復帰を行えるように支援を行っています。
復学後も継続的に登校できるよう、ご家庭に合ったサポートを続けています。
GoTodayについての詳細は、こちらをご確認ください。
最終更新日:2024年8月16日
中学生男子ならではの不登校の主な原因
- ママ、ママと親離れができず、依存が強い
- 自分の気持ちを他人にうまく言えない
中学生男子の不登校の主な原因として、「母子依存による自立の不足」があります。
男子の場合、問題は表面的に現れやすく、依存や自立の欠如が明確に見えることが多いです。
一方で、中学生女子は、表面上はしっかりしているように見えるものの、内心では葛藤や不安を抱えていることが多いです。
女子の場合、親御さんも「しっかりしているからなんとかなるだろう」と感じやすく、問題の深刻さを見過ごすことがありますが、男子は問題が表面化しやすいことが多い傾向にあります。
男子と女子でも、問題の現れ方や親の対応に違いがあることがポイントです。
ママ、ママと親離れができず、依存が強い
男子は女子に比べて精神的な自立が遅れがちで、親子関係に依存する傾向があります。
中学生になっても親と一緒に過ごす時間が長く、他の子どもたちが自立している中で、依存心が強い男子は人間関係で苦労しやすくなります。
男子の場合、親が積極的に「子離れ」を意識しない限り、自然に自立しづらく、子どもは「今の親子関係は世間でも当たり前」と思い込み、学校でもクラスメイトや先生に求めます。
例えば、
- 中学生になっても一人で寝られず、母親と一緒に寝ている
- 父親や母親を「ママ」「パパ」と呼び続ける
- 周りの目を気にせず母親と一緒に買い物やファストフード店に出かけることにも抵抗がない
親子関係がまるで「友達」のような状態になることもあります。
このような過度な依存は、「同級生との価値観や人間関係のズレ」を引き起こし、学校生活での孤立や不登校に繋がりやすくなります。
さらに中学生男子は「親への暴言や暴力」が発生する場合も多い傾向があります。
普段は親子の仲が良いように見えても、母親が自分の意にそぐわない言動を取ると、急に感情をぶつけたり、強い言葉で反発するケースがあります。
他人には本音を出せない男子が、唯一母親に対してだけ感情を爆発させます。
こうした依存状態に親が気づくことは難しいです。親自身は仲の良い親子関係と思っているかもしれませんが、外部の目で見たときに初めて「異常だ」と気づくことも少なくありません。
こうした親御さんの特徴として、子どもから暴力や暴言を受けた時に一時的に嫌な気持ちになるのは当然ですが、すぐに「子どもが可愛い」「話したい」という気持ちが湧き上がり、結果的に子どもを許してしまうケースが見られます。
このような親の対応は、子どもに「何回でも暴言や暴力をしても大丈夫だ」という誤ったメッセージを与えてしまいがちです。
子どもは親の感情の揺れを敏感に感じ取り、自分の行動が繰り返されても問題ないと勘違いしてしまうことがあります。
そのため、親御さんが毅然とした対応をしていくことが重要です。
親は子どもの自立を意識して、できる限り子どもに考えさせたり、日常的に子ども自身がやるべきことは親は口を出さずに任せることが重要です。
責任を持たせることで少しずつ自立を促しましょう。
自分の気持ちを他人にうまく言えない
不登校の中学生男子は、内弁慶になりがちな傾向があります。
つまり、家では自己主張が強いものの、外では自分の気持ちをうまく言えず、黙り込んでしまうことが多いのです。
この背景には、お子さんの性格もありますが、親の過干渉や先回りが原因となる場合があります。
親がまるで「子どものマネージャー」のように、子どもの気持ちを代弁してしまう、「子どもはこう思っているだろう」「こうしてほしいはずだ」と、子どもの本心を聞く前に、親が憶測で対応してしまうことがよくあります。
例えば、先生や他の大人が子どもに何かを質問したとき、親がすぐに口出しして代わりに答えてしまうことがあります。
質問をされているのは子どもなのに、親が「〇〇はこう考えてます」「〇〇はこれが好きなんですよね」と答えてしまうのです。
このような対応は、子どもが自分の気持ちを表現する機会を奪い、次第に「自分の意見を言わなくても、親(他人)が理解してくれる」と思い込むようになります。
結果として、学校や友人との間でも自分の気持ちを言い出せず、心の中で思っていることを外に出せない状態に陥ります。
中学生男子ならではの不登校の特徴
- 不安や焦りをうまく言葉にできず、代わりに怒りや暴力といった形で表現してしまう
- 「自分で問題を解決したい」という強い気持ちがあるため、干渉を拒み、自分で何とかしようとする
- 女の子に比べて、同時に複数のことをこなすのが苦手で、一つのことに集中する傾向が強い
- おしゃべりが少なく、必要なことしか話さない。話しながら感情を共有するのではなく、体を動かして関係を深める
中学生男子は時に、母親から見ると理解しづらく、不可解な行動を取ることがありますよね。
家にいる間、息子がゲームやYouTubeに没頭し、食事やお風呂を後回しにする姿を目にすることもあると思います。
注意をすると、「わかってるよ」と言いながらも、同じ行動を繰り返す。これが毎日のように続くと、親としてどうすればいいのか悩んでしまうのは当然です。
「もうやめなさい!」と叱ると、穏やかだった息子が突然怒りだし、壁を殴ったり、予想もしなかった行動を取ることがあります。以前の彼とはまるで別人のように見えることもあるかもしれません。
しかし、こうした行動には、彼らなりの理由があります。
このような言動は実は「このままではダメだ」「なんとかしなければ」という焦りから来ています。
中学生男子はその不安や焦りをうまく言葉にできず、代わりに怒りや暴力といった形で表現してしまうことがよくあります。
中には、自分が病気ではないか、ゲーム依存なのではないかと密かに悩んでいる子もいますが、男子は弱みを見せることを嫌がるため、それを親に伝えることはほとんどありません。
また、中学生男子には「自分で問題を解決したい」という強い気持ちがあります。
このため、干渉を拒み、自分で何とかしようとします。これは男子の特徴の一つで、特に「戦い」や「勝負事」が好きで、男子特有のものです。
もう一つの特徴として、男子は女の子に比べて、同時に複数のことをこなすのが苦手です。
脳科学の研究によると、女性はバランスよく複数のタスクを処理できるのに対し、「男性は一つのことに集中する傾向が強い」と言われています。
このため、男子はテレビやスマホゲームに長時間夢中になり、他のことが後回しになることがよくあります。
お母さんも、息子に話しかけても反応がなかったり、逆に「うるさい!」と言われてしまう経験がありますよね。
これは男子特有のもので、決して病気だからとか反抗心だけから来るものではないのです。
女子と比べて、中学生男子は会話が少なく、必要なことしか話さないことが多いです。
女子はお互いに話しながら感情を共有し、親密さを深める傾向がありますが、男子は会話よりも体を動かす遊びを通じて関係を築くことが一般的です。
お母さんが息子の気持ちを理解しようとして会話しようとしても、男子にとってはそれが「うざい」と感じられることがあります。
ですが、中学生男子特有の行動を理解することで、関わり方が見えてくるはずです。
不登校の息子が家で一日中ゲームをしていると、お母さんとしては「どうして勉強しないの?」「規則正しい生活ができないの」「学校に行かないならせめて家事をやって」「運動すれば良いじゃん」と不安や心配を子どもに伝えても
しかし、男子は一度に複数のことをこなすのが難しく、さらに不登校という状況では、精神的にも不安定な状態にあります。そんな時、楽な方に流れるのは自然なことです。
問題行動を認めるわけではありませんが、息子さんの行動を「男子ならではの特徴」として理解し、息子は病気なのか?脳がおかしくなったのか?など考える前に焦らないことが重要です。
中学生男子ならではの対応策
中学生男子は子供扱いしない
中学生男子への対応では、子ども扱いをしないことが非常に重要です。
この時期の男子は、「自分」を確立することや、自分を認めてもらいたいという気持ちが強くあります。
ですので、親御さんの言葉かけ一つで大きく反発されることもあります。
例えば、父親が「今勉強しないと将来大変なことになる」と説教じみた言葉を使うと、息子は反発心を抱きやすくなります。
正論を言うのではなく、「自分で気づく機会を与える」ような言葉がけが必要です。
子どもが考えたことがたとえ間違っていたとしても、まずは自分で考え、経験させることが重要です。
兄弟や他人と比較しない
兄弟や友達と比較することも避けるべきです。
中学生は、他人からの評価や外見に対して非常に敏感です。
特に、容姿や体格の違いにコンプレックスを抱えていることが多く、これらのことに触れると、プライドを傷つけてしまうことになります。
一方で、彼らは「自分はできる」というプライドも持っています。
このプライドを正論で壊してしまうと、「じゃあ、もうやらない」とへそを曲げ、「あえて何もしない」ことにプライド持つようになる可能性があります。
そうなってしまうと、本人にとっても家族にとっても大きなマイナスです。
ですから、中学生男子との接し方では、「自分で考えさせる」「失敗してもすぐに正すのではなく、経験させる」「比較や決めつけを避ける」ことが鍵です。
自分の力で物事に取り組み、成功や失敗から学ぶ機会を尊重することで、彼らの自立心を育てていくことができます。
中学生男子の復学事例
中学生男子の復学事例を掲載します、

約1年不登校・部屋の戸をガードして引きこもり、食事も自室に持って食べていました。
息子は部屋に引きこもり、部屋の戸をガードしていました。家族がいる時は食事を部屋に持って行き、夜中に夜食でラーメンなどを煮て食べていました。不登校期間は11ヶ月でした。
息子の部屋はカーテンを閉めて暗くし、全く外に出ず運動もしないため、成長期の体への影響が心配でした。
このまま引きこもりが続くのではないかと不安でした。
ブログでGoTodayという復学支援があることを知り、他の方々もGoTodayの支援で復学されていました。
家にいながら支援を受けられることを知り、「ここしかない」と思いました。
復学支援を受けて、私の対応が息子の性格に合っていない子育てをしていたことが分かりました。
支援を受けてから、息子は一週間で部屋で食べていた食事を一緒に食べるようになりました。
以前は「うるせー」と言われることがありましたが、それもなくなりました。
私は心配性で、忘れ物や宿題のことが気になって声をかけていましたが、今は息子に任せることができ、気にならなくなりました。
息子も以前は泣き言を言ったり物に当たったりしていましたが、指導通りに対応を変えると物に当たることがなくなりました。
今では息子はタブレットを見るために朝早く起き、6時頃には学校のカバンや体育着を持ってリビングに降りてきます。毎日決まった時間に、強い雨でも歩いて学校に行っています。
家に帰ってくると「ただいま~」と言って帰ってきます。
息子の元気な姿を見ることができ、本当に感謝しています。
以前のように陰で泣いていた日々に戻らないように、引き続き家庭教育に取り組んでいきます。どうかこれからもよろしくお願い致します。
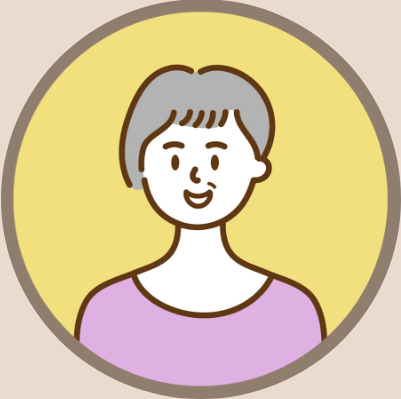
3年4ヶ月不登校・音や匂いに敏感になり、食事も喉を通らなくなっていました。
息子は小学5年生の時から給食が食べられないと言い出し、心身の不調がだんだんひどくなり、学校に行きにくくなりました。
それからは音や匂いなど様々なものに敏感になり、家での食事量も減り、食事が全く喉を通らなくなり、学校に行けなくなりました。
外にも出たがりませんでした。病院に半ば無理やり連れて行きましたが、情緒面でかなり幼いと言われました。
小学6年の終わり頃、主人の仕事の都合で他県へ引っ越しました。
転校してすぐや中学になってすぐは学校に行こうとしていましたが、気分が悪くなり半日もせずに帰るような状況で、中学1年生の始め頃からはまた全く行けなくなりました。
中学1年の中頃から市のフリースクールには週に一度個別対応で1時間ほど行っていました。
体調は徐々に落ち着いてきて、食事量が増え、様々なものへの敏感さも落ち着きましたが、外へは出たがりませんでした。
不登校期間は3年4ヶ月ほどでした。
初めは子供の心身の不調が治ってほしい、どうしたら治るのか、いつ治るのかと非常に不安でした。
そのために病院や市の支援などに相談しましたが、「ゆっくりさせましょう」と言われました。
徐々に息子の状態は落ち着いてきましたが、不登校期間が長くなるにつれて、このまま見守っているだけで社会に戻れるのか不安が増していきました。
弟もお兄ちゃんが家にいることをズルいと感じて休みたがる日があり、弟も不登校になってしまうのではと不安になることもありました。
息子が少し落ち着いた頃、親の不調と過干渉が息子の不調の原因だと考え始めましたが、どう子供に接したらいいのか分かりませんでした。
そんな時、図書館で「ある日、うちの子が学校に行かなくなった」に出会いました。復学率100%に惹かれたのはもちろん、「親が変われば子が変わる」という言葉に強く共感し、指導をお願いすることにしました。
当初は「子供がまた不調になったらどうしよう」と不安でしたが、夫が「お金よりも今は子供が社会に出ていけるようになることが大事」と言ってくれ、GoTodayにお願いすることになりました。
子供への過干渉に気づいてからは、接し方に気をつけていましたが、ご指導を受けて「まだまだ私が心配だから」「私がこうした方がいいから」と接していることに気付きました。
子供が自分なりのペースで考えて動くのを待つと、徐々に自分で行動するようになりました。
ご指導で背中を押してもらった息子は、毎日学校に行き、高校受験を終えて電車通学をして学校に通っています。
表情も明るくなり、目に力が戻ってきました。
私は、人の目を気にしたり周りからの意見に影響されて子供に対応してしまうことがありましたが、子供にとっては辛いことだったのだと改めて思いました。
子供の前では毅然とした態度で、学んだ親の対応を自信を持って実行していきたいと思います。本当にこのご指導に出会えて良かったと感謝しています。

鉛筆を持つと息苦しいと荒れ、五月雨登校・別室登校・完全不登校を繰り返していました。
息子が小学6年生の一学期、コロナ休校明けから月に1〜2回ほど休むようになりました。
中学受験を目指していましたが、鉛筆を持つと息苦しいと荒れるようになり、夏休み明けの二学期に入ってすぐ中学受験を諦めることを決めた翌日から五月雨登校が始まりました。
そして、9月のシルバーウィーク明けに完全に学校に行けなくなりました。
私は過干渉、過保護で、毎日「学校どうするの?」と声をかけていました。
そんな私の声かけに応えるように、息子は時々別室登校や放課後登校をしていましたが、結局、小学校の卒業式にはみんなと出席し、中学からは頑張ると宣言しました。
しかし、中学に入学して張り切って毎日登校していたものの、3週間後のゴールデンウィーク明けから再び全く学校に行けなくなりました。
息子が不登校になり、スクールカウンセラーや民間の不登校カウンセラー、親の会、不登校を診てくれる小児科などあらゆる相談機関に相談しました。
しかし、どれも「できたことを褒めましょう」「動き出すまで待ちましょう」「長男は学校を諦めたほうがいい」というアドバイスばかりで、全く解決に繋がりませんでした。
その間、息子はますます家に閉じこもるようになり、学校に行くきっかけを失っているのではないかと感じていました。
さらに、息子には弟が2人おり、長男の不登校初期には弟たちも引きずられるように学校に行けなくなった時期がありました。
父親が全く理解がなく、長男に当たり散らし、家庭崩壊の状態になっていたことも辛かったです。
長男の不登校初期からGoTodayの存在は知っていましたが、家庭崩壊しているような状況では引き受けてもらえないのではないか、もし引き受けてもらえなかったら頼るところがなくなると思い、相談できませんでした。
しかし、中学に入って再び学校に行けなくなった時、再度ホームページや本を読み、「母親が変われば子も変わる」という言葉にかけてみたいと思い、思い切って申し込みました。
主人にも「私が頑張るから」と説得しました。
「決意して、絶対私が変わる!」と意気込んで申し込みましたが、指導を受け始めた時は自信がなく、不安になることもありました。
しかし、毎日電話で指導していただき、叱咤激励してもらいながらなんとか毎日こなしていました。
ご指導いただいた通りに対応した結果、まず変わったのは主人でした。主人は激変し、とても安定しました。
その後も熱心なご指導を受け、二人の弟も見違えるように自立できるようになりました。
私は以前、良かれと思ってしていた対応が過保護、過干渉であり、子供たちにとって良くない対応だったことに気付きました。
自分の理想を子供たちに押し付け、コントロールしようとしていたことも分かりました。
今では子供の力を信じて待つことができるようになり、自分自身も楽に生きられるようになりました。
長男も今では毎日当たり前のように学校に登校しています。
苦手な授業や行事もやり過ごすことを覚え、友達と楽しく学校生活を送っています。
部屋に閉じこもっていた頃とは全く違い、苦手なことも乗り越えられるようになりました。
GoTodayのご指導により、家庭が救われました。本当に感謝しています。
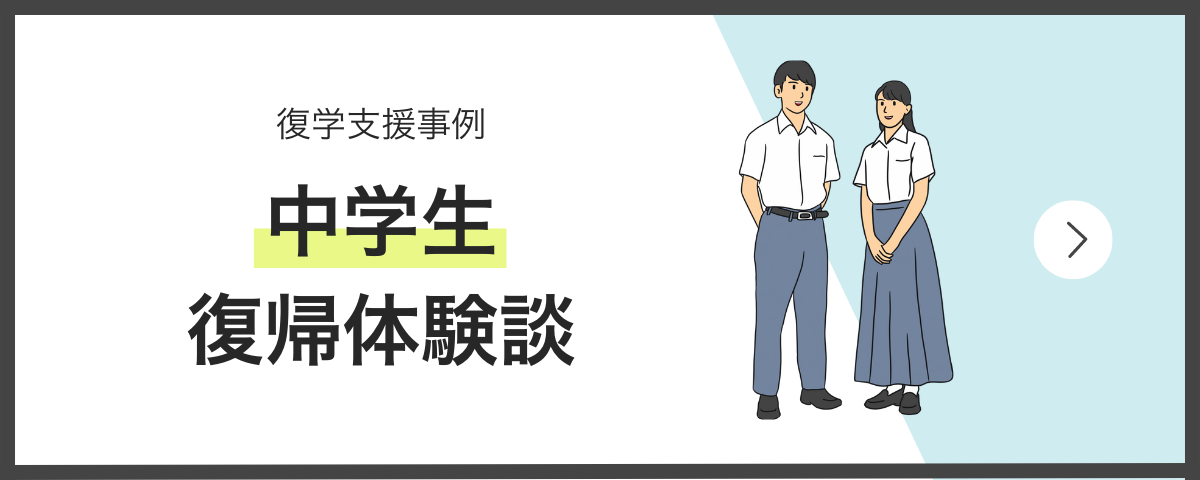
その他の中学生の体験談はこちら
GoTodayの復学支援
Gotodayは「親が変われば、子は変わる」という考えを基本に親御さんが自身の対応を見直すことで、間接的にお子さんが代わり、自立心や協調性が育めるよう支援を行っています。
中学生男子の不登校では、特に家庭内での問題行動が増え、親御さんが対応に悩むケースが多く見られますが、GoTodayでは、中学1年生から3年生、短期間から長期間の不登校まで、それぞれの状況に合わせた支援を行っています。
復学までの期間は支援開始から約3ヶ月〜4ヶ月です。
不登校でお悩みの親御さんはぜひご相談ください。

GoTodayの復学支援の内容・料金の詳細はこちら
下記のページでよくあるお悩み別に考え方や対応策を書いていますので、お子さんの状況に合った内容をお読みいただければと思います。
まとめ
- 母子依存による自立不足
中学生男子は母親への依存が強く、精神的な自立が遅れがちです。親離れができていないため、学校生活や人間関係での困難を感じやすく、不登校につながることがあります。中学生男子は親が「子離れ」を意識しない限り、自然に自立しにくくなりがちです。
- 自分の気持ちを他人にうまく伝えられない
男子は、家では自己主張が強い一方、学校や外の環境では自分の気持ちを言い出せず、内弁慶になる傾向があります。親が子どもの気持ちを代弁したり先回りしすぎることで、自己表現の機会を奪い、他者とのコミュニケーションが苦手になります。
- 家庭内での感情の爆発
男子は親への依存が強いため、親に対してだけ感情を爆発させることがあります。暴言や暴力が発生する場合もあり、親が毅然とした対応を取らないと、依存関係が悪化する可能性があります。
- 親の対応が問題を見過ごす原因に
中学生男子は問題が表面化しやすいものの、すぐに暴力や暴言を許してしまうと、問題の深刻さを認識しにくいことがあります。親が毅然とした態度を取り、自立を促すことが重要です。
- 不安や焦りをうまく言葉にできず、代わりに怒りや暴力で表現することがある。
- 「自分で問題を解決したい」という強い気持ちから、親の干渉を拒む傾向が強い。
- 複数のことを同時にこなすのが苦手で、一つのことに集中しやすい。
- 女子に比べて会話が少なく、必要なことしか話さない。感情の共有よりも体を動かして関係を深める傾向がある。
- 子ども扱いしない
中学生男子は自分で物事を進めたいという強い気持ちを持っているため、子ども扱いをしないことが重要。親からの正論や説教は反発を招きやすいので、自分で気づかせる対応を心がける。
- 自分で考えさせる
たとえ間違った選択をしても、自分で考えて行動させ、経験を通して学ばせることが大切。
- 兄弟や他人と比較しない
他人や兄弟との比較は、プライドを傷つけやすく、反発心を生む可能性があるため避ける。
- 失敗を許容し、経験させる
失敗してもすぐに正さず、自分自身で学び、自立できる機会を与えることが大切。