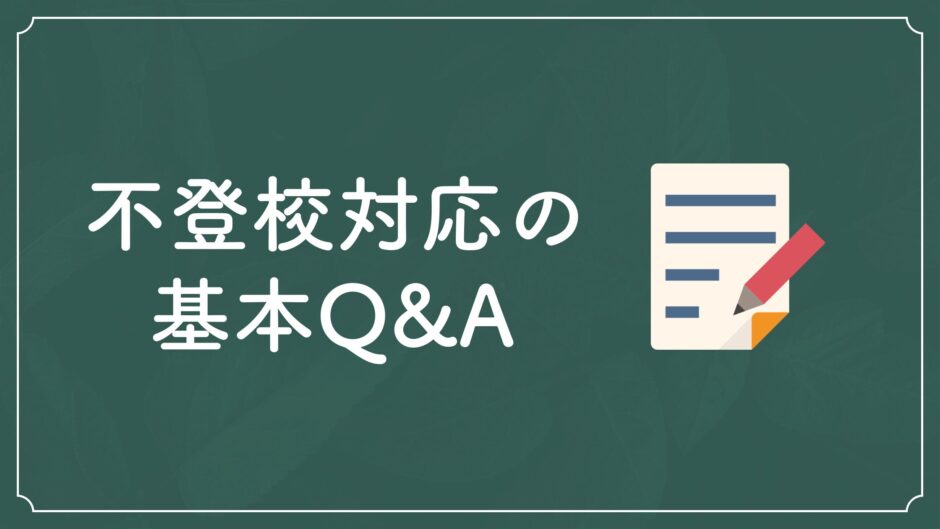このページでは、ちょこっと相談、復学支援を受けていただく前の個別面談でよくいただく質問や悩みをもとにまとめています。
不登校に向き合う親御さまにとって一つでも新たな気づきや安心につながり、このページを通じて不安を少しでも軽減できれば幸いです。
ここでお伝えする回答や対応は、あくまでも基本的なものになります。
熱心な親御さんはご自身でも対応されるかと思いますが、ご家庭の状況によっては悪化する場合もありますので、参考程度にとどめていただき、個別で相談されたい方はちょこっと相談や個別面談を受けていただければ幸いです。
GoTodayの利用案内についてのQ&Aはこちらのページでまとめています。
2025.9.16
「寄り添いましょうとアドバイスを受け、対応していますが、上手くいきません。不登校にどう寄り添えば良いですか?」を追記しました。
「「子どもは褒めて伸ばしましょう」と言われますが、褒め方がわかりません。また、不登校でも褒めた方が良いでしょうか?」を追記しました。
2025.8.31
「不登校になる理由はなんですか?」を追記しました。
「母親は仕事を辞めた方が良いですか?」を追記しました。
「不登校中のデジタル制限はどうすれば良いですか?」を追記しました。
「「明日は学校に行くからスマホを貸して欲しい」と言われたらどう対応すればいいですか?」を追記しました。
不登校の基本
不登校とはどういう状態を指すのですか?
文部科学省では「病気や経済的理由以外で、30日以上連続して欠席している状態」を不登校と定義しています。
ただし実際には、30日を待たなくても「行き渋りがある」「五月雨登校(行ったり行かなかったり)」「母子登校(母親の付き添いでないと登校できない)」「遅刻早退がある」などの時点で不登校と捉え、対応を始めることが大切です。
Go Todayでは、数字の基準よりも「子どもの状態」に注目し、早めに対策することを重視しています。
不登校になる理由は何ですか?
文科省の調査では「無気力・不安」が最多ですが、実際には「いじめ」「友人関係」「勉強のつまずき」など複合的です。中には「理由が分からない」ケースも少なくありません。
Go Todayでは不登校の背景は、完璧主義や不安が強い、親子関係での依存など、表面だけでは分からない理由が多く隠れていると考えています。
Go Todayでは「子どもを直接変える」のではなく、親御さんが落ち着いて対応できるようになることが第一歩だと考えています。親が焦らず対応できると、子どもも安心して次の一歩を踏み出せます。
「原因探し」にこだわらず、親の関わりを整え、子どもが自立心を取り戻せる環境づくりを第一に考えています。
詳しくはこちらの記事でも解説しています。
親の対応
母親は仕事を辞めた方が良いですか?
不登校になると「子どもが家にいる間は、母親は仕事を辞めて寄り添うべきでは?」と悩む方は少なくありません。ですが、Go Todayは 「母親が仕事を辞めても不登校は解決しない」 と考えています。
不登校の背景には、完璧主義・人間関係・親子関係の偏りなど、さまざまな要因があります。「母親が働いているかどうか」が直接の原因になるケースはほとんどありません。
むしろ、母親がそばにいすぎると「母子依存」を強め、子どもの自立を妨げる場合もあります。
詳しくはこちらの記事で解説しています。
不登校中のデジタル制限はどうすれば良いですか?
不登校の間は、学校の時間帯にスマホやゲームを制限することが望ましいです。学校に行っていれば本来使えない時間帯なので、家庭内でも「学校の時間はデジタルを控える」というルールを示すことは必要です。
ただし、完全に禁止する必要はありません。家庭によって調整すればよく、無理に制限すると強い反発を招くこともあります。
特に小学生高学年〜中学生では、親御さんだけで対応するのが難しい場合もあります。その際は無理をしないようにしましょう。
デジタルは一律に「悪」と捉える必要はなく、あくまでも家庭のルールと信頼関係を基準に「使える範囲」を決めていくことです。
GoTodayの支援でも、不登校中も完全に制限したり、無理やり取り上げたりすることはなく、節度を持って使用するようにしてます。
「明日は学校に行くからスマホを貸して欲しい」と言われたらどう対応すればいいですか?
スマホを渡すかどうかは、その時の状況によって判断することが大切です。
基準は「かわいそうだから」ではなく、「これまで約束を守ってきたか」「言葉と行動が一致しているか」といった“信頼関係”に置きましょう。
「(やるべきことを)やらなくても欲しいものは手に入る」と子どもが学んでしまうと自立(学校復帰)が遠のきます。一方で「行動すれば信頼され、自由も広がる」と経験できれば、学校生活や将来に必要な力が育ちます。
もちろん、子どもは反発して「なんで貸してくれないの?」「友達は制限されていないのに」「スマホがないとエネルギーがたまらない」などと、親を納得させようとする“お決まりの言い方”をよくしてきます。
でも、こうした言葉にいちいち振り回される必要はありません。大切なのは言葉ではなく「実際の行動が伴っているかどうか」です。不登校であっても、親が態度で一貫して「信頼は行動で築かれる」という姿勢を見せ続けることが必要だと考えています。
寄り添いましょうとアドバイスを受け、対応していますが、うまくいきません。不登校にどう寄り添えば良いですか?
寄り添っているのにうまくいかないと、どうすれば良いか困ってしまいますよね。
その原因のひとつに、寄り添っているつもりが、それが寄り添い過ぎて、気づけば子どもの機嫌を取る関わりになっていたり、家庭内での立場が逆転し、お子さんの自立心や協調性も育まれなくなっていることです。
寄り添いというのは、あくまでも親子の関係性を修復するためのもので、寄りそいすぎると、自立心や協調性が育まれず、家では偉そうにしても外では自分を出せないような「内弁慶」になることもあります。
そうなると、ますます学校に通えるようにはなりにくいです。
まずは、寄り添い方を見直して、今の関わりが寄り添いすぎて過保護・過干渉になっていないか、子どもをわがままにしていないかを意識して接してみてください。
こちらの記事も参考にしていただけたらと思います。
「子どもは褒めて伸ばしましょう」と言われますが、褒め方がわかりません。また、不登校でも褒めた方が良いでしょうか?
「褒める」って、どこを褒めればいいのかよくわからない。褒めたら図に乗らないかもなど…と悩みますよね。
ポイントは、「結果を褒めるのか」「努力や意欲を褒めるのか」 にあります。
多くの親御さんは「結果」を褒めがちですが、結果は子どもがいつもコントロールできるものではありません。そのため「また同じ結果を出さなきゃ」とプレッシャーになり、不安ややる気の低下につながることがあります。
一方で「努力や意欲」は自分でコントロールできるものです。「工夫してやってみたね」「最後まで取り組んだね」と声をかけることで、子どもは勇気づけられ、次の挑戦にもつながります。
私たちができるのは、次も子どもが良い結果を出すように褒めるのではなく、次も良い結果を目指して努力できるように認めることです。それが、自信や自己肯定感を育て、復学にもつながっていきます。