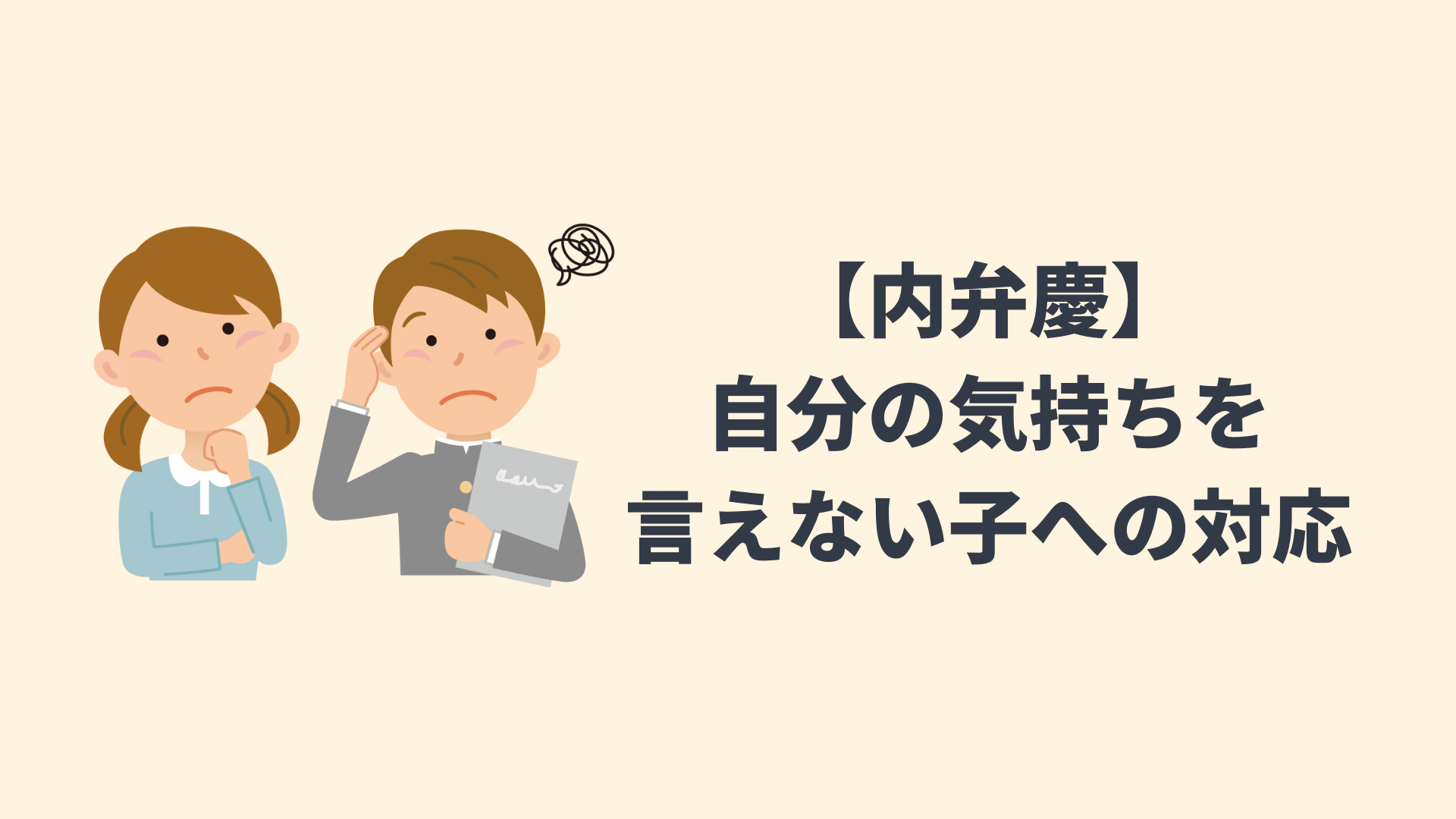こちらの記事は2024年2月7日に更新されました
- 「いらない」
- 「知らない」
- 「後でやる」
- 「わかってる」
- 「でも」
このように、親からの働きかけに反発・反抗するお子さんに悩んでいませんか?
親であるがゆえに
「言ってあげなければ」
「手助けしなければ」
「しつけをしなければ」
などと考え子育てをしてきた親御さんも多いと思います。
しかし、子どもが行動を起こす前に、親が動きすぎると「子どもの自立」によくありません。
その理由について書いていきます。
ぜひ参考にしていただけたらと思います。
反発・反抗させない対応
「どのように考えて生活していくか」
「困難なことに直面したときに、どう切り抜けていくか」
を子ども自身に考えさせる。ということが大切です。
「失敗は成功のもと」
という考えがあるように、子どもも失敗の連続で成長していく。
ということを忘れてはいけません。
初めに書きましたが、
子どもが行動を起こす前に、親の知恵で解決させようとしてしまうと、
「うん、うん」だけ言う子、「いや」と反発・反抗する子になります。
親が子どもの悩みを解決してしまえば、早く解決するのですが、
子ども自身が物事を考える時間がなく、頭が混乱し、考える思考力がなくなります。
そうすると、子どもは落ち着きのない子、集中力が続かない子という状態になってしまうのです。
特に不登校でお子さんが1日中家にいると、勉強や手伝いなど、
少しでもさせたほうが良いのではないか?と思うと思います。
しかし、ほとんどの場合、
母:「〜したら?」
子:「やらない」「わかってる」「でも」「後でやる」
という会話になり、反発させて終わることがほとんどです。
事例1.2
よくある会話事例を紹介します。
- 母:「塾に行ったほうがいいんじゃないの?」❌
- 子:「勉強が必要だと思うから塾に行きたい」⭕️
と自分から言ってくる子どもにしなければいけません。
親が「うちの子は勉強が苦手だから塾に行かせたほうが良い」
と思って子どもに話しても、
子どもは話を聞いているだけで、
「うん」
「いらない」
「いる」
「でも」
しか言わなくて済むので、あとは親がすべてやってくれます。
「うちの子は、うん、いらない、知らない、別に、しか言わないんですよ」
とよくご相談を受けますが、
このようなケースでは、
親がなんでもかんでも、子どもが考える前に解決策を話してきた結果です。
子どもに考えさせる家庭教育が大切です。
しかし、なんでもかんでも、子どもに判断を任せればよいということでもありません。
お子さんの年齢や性別などによっても変わってきますので、
具体的な対応については復学支援の中でお伝えしています。
- 子:「つまんない」
と1日中家にいるお子さんが話してきたら、なんと答えるでしょうか?
おそらく、ほとんどの親御さんが、
「外で遊んできたら?」
と答えるのではないでしょうか?
ここで大切なことは、
子どもの「つまんない」という気持ちを受け止めることです。
「つまんない」からどうするのかを子どもが自分で考え、
決めて行動できるようにすることが大切です。
子どもが学年が低く素直な時は良いのですが、
学年が上がるごとに
「でも、でも」
と言い、反発することを覚えさせることになります。
具体的に、【どのように受け止めるか】については、指導の中でお伝えしています。
自分の気持ちを素直に言えない子
学校などの集団生活で自分の気持ちを素直に言えない子は、自分で考える前に、物事の筋道を言われてきたお子さんが多いです。
家庭の中で「自分の考えを言う練習」ができていないのです。
思っていることを言葉にして言えないようになります。
一番大きな問題は、学校などで友達から何か言われても、「でも・・でも・・」と言い訳ばかり答えたり、友達に自分の考えをうまく伝えられず、友達付き合いが難しくなり、相手にされなくなってしまうことです。
まとめ
不登校のお子さんをもつ親御さんは、毎日の対応についてとても悩まれていることと思います。
お子さんの性格と親御さんの対応が合わないと、子どもに問題行動が起きやすくなります。
不登校のお子さんは、繊細で周りの影響をとても受けやすいため、親の対応一つ一つで子どもの成長も大きく変わってきます。
今回書かせていただいた内容は、復学支援を受けている方や面談でもよくご相談のある内容です。
ご自身だけが悩まれていると思わず、皆共通の悩みを持っていること。
親が変われば子どもも変わる。という考えがある。
そのように考えていただけたら幸いです。