●1日中スマホやゲーム、ユーチューブばかりで勉強もせず困っている
●朝起きず、夜中までタブレットとTV漬けになっていて昼夜逆転している
●ゲームやスマホ、タブレットを要求する暴力に困っている
Go Todayでは、これまでゲーム・スマホ依存、昼夜逆転、その他生活習慣の乱れている子どもの復学を多く行ってきました。
このようなお悩みを解決するためのGo Todayの考え方・方針をお伝えします。
GoTodayの考え
Go Todayでは、根本的な解決をするために、「親が変われば、子は変わる」という考えを基本に、親の子育てに対する対応・考え方の変化が子どもの変化を促すと考えています。
「親が子どもに合った対応を学び、実践することで、子どもが自立し、協調性を持つようになる」という考え方です。
親としては、子どもが学校に行かず、外にも出ず、1日中、スマホ・ゲームをやって昼夜逆転している姿を見ると、この生活が将来の自立にどう影響するのか、心配になりますよね。
Go Todayでは、ゲーム依存や、昼夜逆転、睡眠、食事、歯磨き、風呂などの生活習慣のみに焦点を当てて改善しようとすることは返って状態を悪くすることになると考えます。
なぜなら生活習慣の乱れは、単にゲームや電子機器の執着から生じるだけではなく、学校への不安やイライラからの現実逃避も関係しているため、無理に制限をかけたり正そうとすると反発を招き、親子関係にも影響し、余計に悪循環に陥りやすいです。
そのため、1日でも早く復学を目指すと同時に、学校に行かない期間に生活習慣を無理に正そうとするのではなく、根本的な解決に向けた対策をしてきます。
そして、学校への復学する過程でゲーム、生活リズムの改善も適切に対処していきます。
できる限り本人が自分の意思で管理ができるようになるのが一番良いですが、ある程度、習慣が身につくまでは親が制限をかけていくことも必要になります。
学校に行かなくなり、だんだんと生活リズムがずれ、昼夜逆転したり、歯も磨かず、風呂も入らない、一日中ゲームしている。
特に小学生高学年~中学生はこのような状況になるケースが多々あります。
生活習慣が乱れる理由としていくつか考えられることあります。
- 朝起きてもやることがない
- 朝起きて、学校に行きなさいと言われたくない
- 朝に家族に会うのがイヤだから、母親が出勤するまで時間をずらす。
- 昼間家にいて疲れていなく、眠れないので、ずるずると遅くなる。もしくは、昼間に寝てしまい、夜寝れなくなる。
- 夜遅くまでゲームなどの電子機器を使い眠れない。
などです。
Go Todayでは、全てやりたい放題にさせるのかというとそうではありません。
伝え方、伝えるタイミングがありますので、対策は指導の中でお伝えしています。
とは言っても、特に小学生の高学年~中学生ですと、特に電子機器の取り扱いについては、子どもによっては簡単に親が対策・制限できない場合もあります。
また、制限することで暴れたり、親子関係も悪くなることもありますので、ご家庭の様子によってどの程度制限をかけていくのか見極めながら判断していきます。
GoTodayの方針
Go Todayでは、不登校期間中の生活リズムを整えるために、電子機器の利用は学校の時間帯と夜間は避けるように指導しますが、各家庭ごとに制限の程度やタイミングは異なるので、個別の配慮が必要です。
電子機器の制限については、子どもが暴れるケースもあるため、家庭や子どもの状況に応じて柔軟な対策が必要であり、親子間の信頼関係を損なわないように配慮しながら指導行っています。
制限の仕方も、取り上げたり、いきなり制限をかけるのではなく、子どもが納得する言い方を親御さんにお伝えして、親御さんからお子さんに伝えていただきます。
生活習慣を改善することにおいては、学校への復学を優先し、家族の対応だけでなく、第三者の介入を行い改善を図ります。
第三者の介入による家庭の空気の入れ替えは非常に重要です。
子どもの態度と親の子どもに対する接し方のどちらを改善しやすいかというと、親の接し方を変える方が比較的容易であると考えられます。
子どもは自分の家庭環境を基準にしていて、現状を当然のものとして受け入れている場合が多いので、親が注意しても反発されるか、受け流されて一時的には辞めますが、本人の意思で守っている状態からはかけ離れています。
実際に、親から言われることと他の第三者から言われることでは、同じ内容であっても受け入れ方が異なります。
第三者の介入によって、子どもたちは自分の家での生活習慣を客観的に知ることができ、変化を促すことができます。
学校に戻し、毎日教室へ継続登校させることが大前提ですが、最終的な目標は、子どもが社会性を育み、不登校期間中の生活リズムや生活習慣の改善を通じて、子供の自立と社会への適応を促すことにあります。
電子機器の取り扱いについては、親御さんだけで行うと、親子の信頼関係にも関わるので、Go Todayの方針を読んで親御さんだけで対応されることは辞めてください。
下記にゲーム依存・昼夜逆転などしていたお子さんの復学事例として挙げていますので、参考程度にご確認ください。
事例・体験談
現在準備中
GoTodayの復学支援
GoTodayでは、一日中YouTubeやゲームをしている子・昼夜逆転し引きこもっている子のケースに多く対応してきました。
最近は、学校でもタブレットが配られて、一層親が管理することが難しくなっています。
お伝えしたGoTodayの考え方・方針を親御さんだけで実行しても、必ずしも簡単に上手くいくものではなく、問題が拗れてしまうこともあります。
GoTodayでは、各ご家庭ごとに、お子さんの生活状況・電子機器の使用状況など面談でよくお伺いし、ご家庭、お子様一人一人に合った対策を考え、指導を行っていきます。

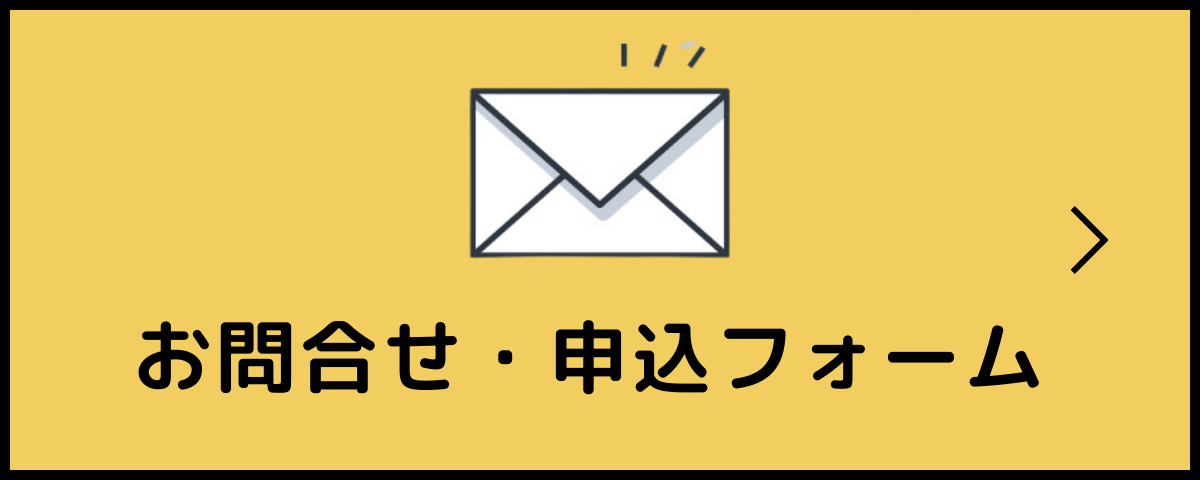
一日中YouTubeやゲーム依存・昼夜逆転している親御さんからよくある質問
- うちの子は一日中YouTubeやゲームばかりで、声をかけても反応が薄いです。Go Todayでは、このような依存状態から抜け出すためにどのように支援しますか?
- はい、YouTubeやゲームに長時間依存しているお子さんへのご相談はとても多くいただいています。
親が声をかけても反応がないと、「このままで大丈夫なのか」と強い不安を感じるのは当然のことと思います。
ですが、いきなり機器を取り上げたり、注意を繰り返すだけでは、親子関係が悪化して逆効果になることもあります。
Go Todayでは、依存しているゲームや動画を不登校の「原因」ではなく、不登校になった「結果」としてとらえます。
お子さんがゲームや動画に没頭する背景には、
・現実のストレスから逃れたい
・何も考えずに過ごしたい
などといった状態が影響していることがほとんどです。
そのため、私たちは「親が変われば子は変わる」という考えのもと、親御さんの関わり方を整えることで、徐々に現実に目を向けられるような心の土台を育てていきます。
依存しているように見えても、お子さんの中には「このままではいけない」という気持ちがあるものです。その気持ちを引き出せるように、家庭の関わり方を整えることが、最初の一歩になります。
- 昼夜逆転して全く生活リズムが整いません。Go Todayの支援を受けることで、規則正しい生活に戻れるでしょうか?
- はい、昼夜逆転の状態からでも、生活リズムを整え、学校に通える状態に戻していくことは可能です。
昼夜逆転は、不登校のお子さんの多くに見られる状態で、決して珍しいことではありません。
ですが、放っておくと心身ともに不安定になり、ますます社会との接点を失ってしまう可能性もあります。
Go Todayでは、「早く寝かせる」「朝起こす」といった直接的な介入ではなく、生活リズムを乱してしまっている背景を理解し、根本から整えていく支援を行います。
たとえば以下のような方法です:
・親御さんの日々の声かけ・接し方の見直し
・子どもが昼夜逆転に“居心地の良さ”を感じないような家庭環境の調整
・朝型の生活に自然に切り替えていくための段階的な関わり
Go Todayの支援は、「親が変われば、子は変わる」という考え方に基づき、親御さんの関わり方を変えることで、お子さん自身が「このままではいけない」と感じる土台を育てていきます。
その結果、無理に押しつけなくても、子どもが自分から生活リズムを整えようとする動きが出てくるようになります。
実際に、昼夜逆転で朝まったく起きられなかったお子さんが、ご家庭の関わりを見直すことで数週間~数か月のうちに朝型に戻り、学校復帰できたケースも多くあります。
昼夜逆転は「叱る・起こす」ではなく、親御さんの関わり方の変化から、ご家庭だけで難しい場合も、どうか一人で抱え込まずにご相談ください。
- 他の相談機関では「時間制限を設けるように」と言われましたが、全く効果がありませんでした。Go Todayの依存に関する支援の特徴は何ですか?
- 時間制限をかけても効果がない、そのようなお悩みは、私たちにも多く寄せられています。
実際、YouTube・ゲーム・スマホなどの依存に対して「時間を決めて」「取り上げて」といった対応をしても、
・親子関係が悪化した
・ますます反発されて制限できなかった
・隠れてやるようになった
というケースは少なくありません。
時間制限や取り上げは、一時的にやめさせることはできても、根本的な解決にはなりません。
Go Todayは、「自発的にやめられる状態」をつくることを重視しています。
ただし、全く放置するのではなく、お子さんの状態や家庭の状況を見ながら、無理のない形で「適度な制限」も取り入れていきます。
いきなり取り上げたり、禁止するのではなく「納得できる形」でルールをつくり、生活リズムや親子関係が整ってきた段階で徐々に制限をかけていく。
このように、段階をふみながら自然に依存状態を改善していくのが特徴です。
